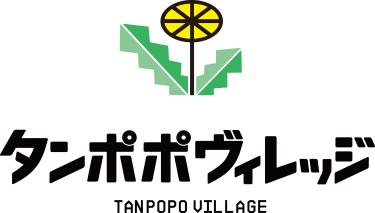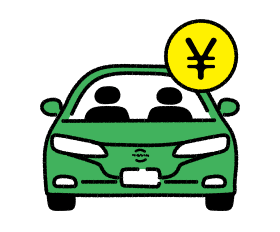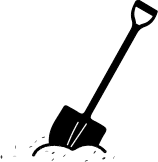知っておきたい!自動車優遇制度を1から簡単に解説!
あなたは自動車に関する優遇制度についてどれくらい知っていますか?
実は購入時だけでなく、所有している間も安くなる制度がたくさんあります。
これらの優遇制度を活用して、今まで少し手が届かなかったクルマを購入できたり、節約したお金を使って躊躇してた旅行ができたりするかもしれません!
今回は「なぜ優遇制度があるのか」から「どんな制度があるのか」について、全く知らない方でもわかるように解説します。
優遇制度を賢く使えば、家計の負担を下げられるかもしれません!
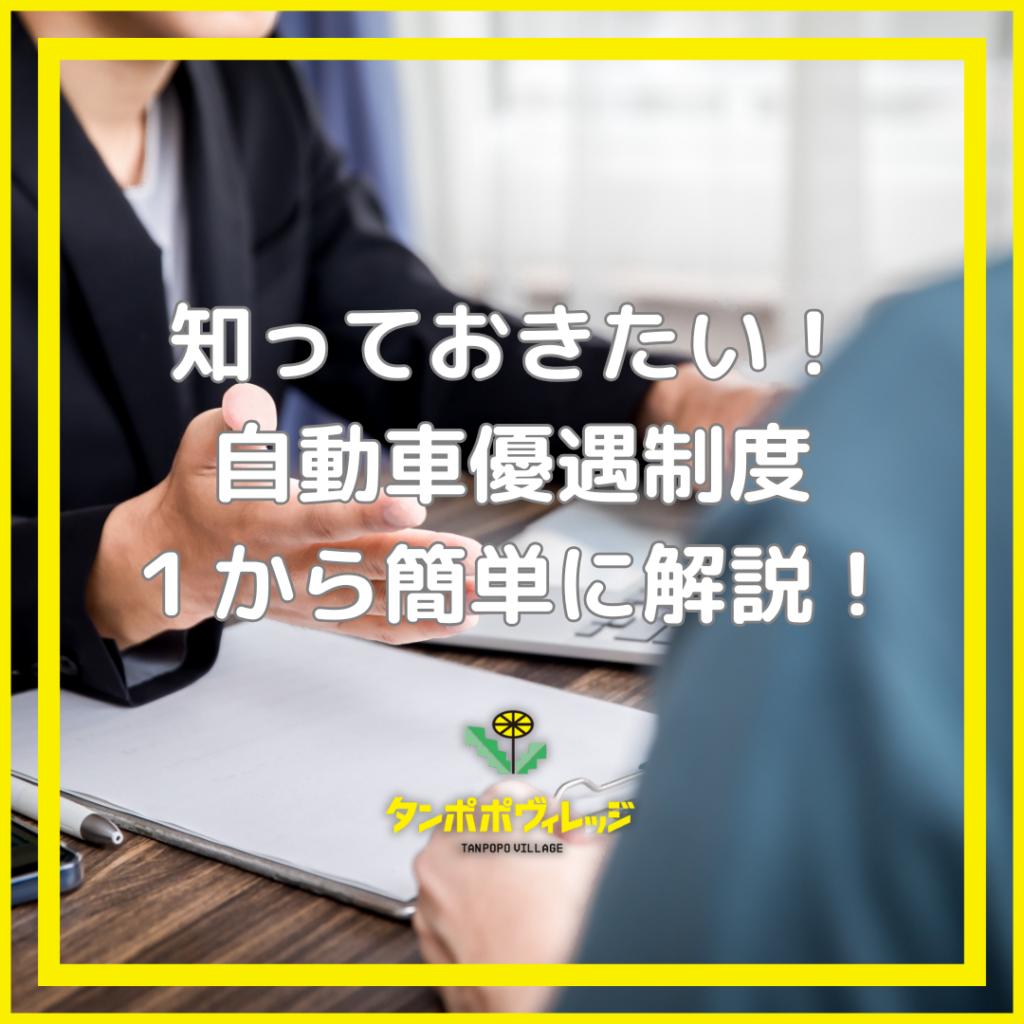
なぜ自動車の優遇制度が存在するの?
購入時や所有時に安くなるとは言っても、理由がわからないと「何か落とし穴があるんじゃ……」と不安になる方もいらっしゃると思います。
まずは理由を知ることで安心して優遇制度について知っていきましょう!
自動車の優遇制度は大きく分けて3つの目的があります。
1.
環境配慮を促進するため
地球温暖化対策として、CO2排出量の少ないエコカーの普及を国や自治体が後押ししています。
例えば、電気自動車は走行中にCO2を排出しないため、ガソリン車1台を電気自動車に置き換えると、年間約1トンのCO2削減効果があるといわれています。
しかし、電気自動車や水素自動車といった次世代自動車は従来のガソリン車に比べて価格が高いため(一般的に100万円以上の差があります)、購入しやすくするための支援策として補助金制度が設けられています。
2.
安全性向上のため
交通事故を減らすために、安全技術を搭載した車両の普及を促進しています。
警察庁の統計によると、自動ブレーキなどの先進安全技術を搭載した車両は、そうでない車両と比べて事故発生率が約40%低減すると報告されています。
保険会社も事故リスクの低い車には保険料を割り引くことで、より安全な車選びを後押ししています。
例えば、自動ブレーキ搭載車は事故率が低いため、保険料が最大9%安くなることがあります。
これは保険会社にとっても支払い額の減少につながるため、まさにWin-Winの関係になっています。
3.
障害のある方の社会参加をサポートするため
障害のある方にとって、自動車は移動手段の一つではなく、社会参加や自立を支えるなくてはならない道具です。
公共交通機関の利用が難しい場合も多く、自家用車が必要不可欠な方も少なくありません。
厚生労働省の調査によると、身体障害者の約60%が外出時に何らかの困難を感じていると回答しており、特に車椅子使用者の方は公共交通機関の利用に多くの制約があります。
そのため、障害のある方が自動車を所有しやすくするための税制優遇や減免制度が設けられています。
それでは、具体的にどのような優遇制度があるのか見ていきましょう!
補助金と保険の割引をチェック!
まずは、エコカーの普及を促進するために作られた補助金についてお話します。
電気自動車の補助金
電気自動車を購入すると、一般社団法人次世代自動車振興センターを通じて国からの補助金を受けることができます。
2024年度の補助金額は、電気自動車の場合、車両価格やバッテリー容量に応じて最大85万円が支給されます。
さらに、充電設備の設置にも補助金が出るケースもあります。
詳細は次世代自動車振興センターのウェブサイトで確認できます。
水素自動車の補助金
水素を燃料とする燃料電池自動車も環境に優しい次世代自動車として、購入時に補助金を受けることができます。
水素自動車の場合、2024年度は車両によって最大255万円の補助金が支給されます。
これは車両価格が高額なことを考慮した措置です。
詳細は次世代自動車振興センターのFCV補助金ページをご確認ください。
次は安全性向上のために作られた保険のお話。
自動車任意保険には意外と知られていない割引があるんです。
自動車保険のASV割引
ASV(Advanced Safety Vehicle)とは、先進安全自動車のことで、自動ブレーキなどの安全運転支援システムを搭載した車両を指します。
このような安全技術を搭載した車は事故を起こす確率が低くなるため、多くの保険会社では「ASV割引」として保険料を割り引いています。
例えば、衝突被害軽減ブレーキを搭載した車両では最大9%程度の割引が適用されるケースもあります。
保険会社によって割引率や条件が異なりますので。詳しくは各保険会社のHPでご確認ください。
新車割引
新車は中古車に比べて安全性が高く、故障のリスクも低いとされています。
そのため、多くの保険会社では新車を購入してから一定期間内であれば「新車割引」として保険料が割引されます。
一般的には初年度登録から25ヶ月以内の車が対象となり、数%から最大20%程度の割引が適用されることもあります。
こちらも保険会社によって割引率が異なるので、詳しくは各保険会社のHPでご確認下さい。
障害のある方への減税制度って?
さらに、障害のある方やその家族向けの優遇もあります。
例えば、愛知県では障害のある方が車を持ち運転する場合や障害のある方の通院の送迎のためにクルマを使う場合に自動車税や取得税が減免される制度があるんです。
車いす対応の車を買うときの補助金もあったりして、生活を支えるサポートが充実しています。
必要な人に必要な支援が届くって、素敵な仕組みですよね。
自動車税・軽自動車税の減免
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳をお持ちの方が所有する自動車については、一定の条件のもとで自動車税や軽自動車税が減免されます。
例えば愛知県の場合、障害の程度や使用目的によって、最大で税額の全額が減免されることもあります。
詳しくは各都道府県の税務課のウェブサイト(例:愛知県の自動車税減免制度)でご確認ください。
自動車取得税・自動車重量税の減免
自動車の購入時にかかる自動車取得税や、車検時に納める自動車重量税についても、障害の程度に応じて減免制度が適用されます。
これらの制度を利用することで、自動車の購入時や維持費を大幅に抑えることができ、障害のある方の社会参加や移動の自由を支援しています。
まとめ
自動車の優遇制度は、環境保護や安全性向上、社会福祉など様々な目的で設けられています。
これらの制度をうまく活用することで、車の購入費用や維持費を大幅に節約することができます!
車選びの際には、購入価格だけでなく、こうした優遇制度も含めたトータルコストで考えることで、より賢い選択ができるようになります。
しかし、次世代自動車への補助金は年度ごとに予算が決まっており、予算がなくなると終了してしまうこともあります。
気になる制度があれば、早めに情報収集して申請することがおすすめです!
ぜひ、優遇制度を賢く使って今より家計の負担を抑えた暮らしを送ってみてはいかがでしょうか?
営業のプロがライフスタイルに合わせた最適解をご提案!!