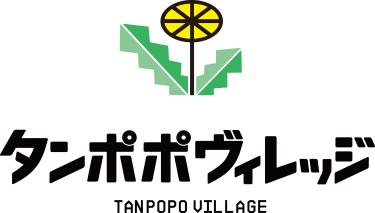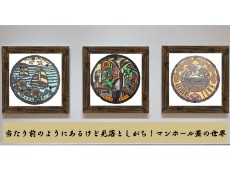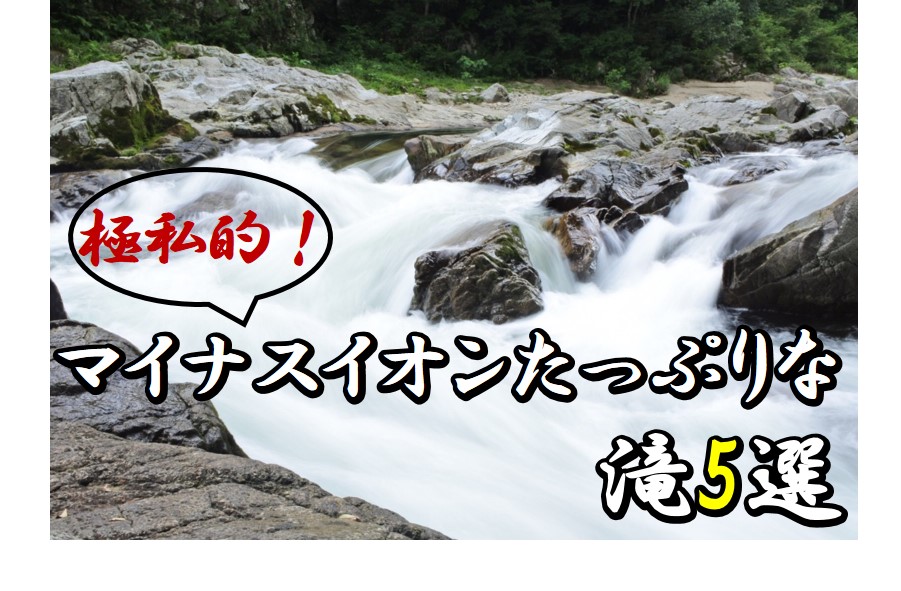これがわたしの懐かしの味 ~豊橋で伝統和菓子探してみた。~

最近、和菓子食べたよって人!てーあげて!
今、画面の向こう側で手をあげている方は、おそらくかなりの和菓子好きなのではないですか?
そう、今回のテーマは和菓子。
洋菓子が普及する何十年、何百年も前から、私たちの心をほっこりと癒してきた存在。
しかし現代では、和菓子の身近さは人によって異なります。
普段からおやつとして食べる人もいれば、お土産でもらう以外はほとんど食べないという人もいるでしょう。
そこで今企画では、秘められし和菓子を愛する本能を呼び覚ますため、愛知県豊橋市にある和菓子店を3店ピックアップ。
それぞれのお店で「おはぎ」「いちご大福」「おすすめの一品」を購入し、筆者と上司が食べた感想を述べていきます。
最近和菓子を食べてない人も、記事を読み終わる頃には和菓子を食べたくて仕方なくなるかも!?
豊橋が誇る和菓子の匠たち!
一店舗目は「ういろう餅昌」さん(以下、餅昌さん)。
下地町の豊川からほど近いこの土地で、ういろうの店として地元民から親しまれてきました。

季節の商品をアピールするのぼりが風にはためいています。

メインのショーケースにはその日に手づくりされた生菓子がずらり。
右手前の棚にはお煎餅が並び、奥のショーケースには誕生餅など予約商品の見本が飾られています。

看板商品は100年近く昔から変わらぬ製法で手作りされているういろう。戦前から続く伝統の味は必食です。
二店舗目の「八町もちや」さん(以下、八町もちやさん)は、国道1号が目の前を通る八町通にて約80年愛されてきた老舗。移転前も含めると約95年の歴史があるのだそう。

店舗の前方には、かつてこの地に建てられていた吉田宿の東惣門を再現したモニュメントが。豊橋の歴史が感じられますね。

店内にずらりと並ぶ、和菓子を入れるケース。商品が売れてしまったので今は空っぽ。

ショーケースには定番ものから季節のものまで数々の商品が並んでいますが、なんと職人さんたちは2時半から和菓子作りを始めているのだそう。
職人さんの朝は早いというイメージはありましたが、ここまでとは……驚きが隠せません。
三店舗目の「和菓子 あづ木」さん(以下、あづ木さん)は往完町の住宅街に佇む隠れ家的なお店。

お店の看板食品である豆大福の文字が踊るのれんと看板が目印。


値札の横には見本が置かれていて、和菓子の中身が見れちゃいます。いちご大福の断面図を見ると購買意欲をそそられるのは筆者だけではないはず。
2021年オープンのニューフェイスということもあり、季節限定商品では洋のテイストを取り入れた現代調の和菓子も楽しめるお店です。
食レポの「ココ見て!」ポイント
それぞれのお店に、雰囲気や商品など違いがありましたね。
今回はその特色を実感してもらうため、まずは同じ和菓子同士の比較をしていきます。
おはぎはお彼岸の行事食として親しまれており、多くの人にとって身近な和菓子なのではと思いチョイス。
昨今ブームのいわゆる「進化系おはぎ」など例外もありますが、人々のイメージにはばらつきが少ないので、見た目よりも味や食感の違いなどに着目して比較していきます。
続いて紹介するのはいちご大福。おはぎとは反対に、比較的発祥が新しい和菓子だからこそお店ごとの個性が出やすい和菓子。
見た目や使っている材料の多様さから、いちご大福の世界の広さを実感できるでしょう。
最後に、それぞれのお店のおすすめの一品での比較も!その理由も合わせて、お店の魅力をご紹介します。
それでは本日の戦利品たちをご覧ください!

3種類×3店舗分の和菓子が集結した様子はまさに壮観。どれも美味しそう……!
我々も食欲が我慢できなくなってきたため、食レポに移ります!
【File1:おはぎ】もちもあんこも千差万別!?あなたの知らないおはぎの世界
おはぎ、それはもち米とうるち米(もち米のみで作る場合もある)を混ぜたものを米粒が残る程度に潰して丸め、あんこをまぶしたお馴染みの和菓子。

(左から餅昌さん、八町もちやさん、あづ木さん)
初めにいただくのは画像右側にあるあづ木さんのおはぎ。

(1個・200円)
まあるい形をしていて、表面にはところどころあずきの粒が。
半分に割ると、もち米のご飯感はあまり残っていないように見えました。
食レポ初めの一口、いただきます。
上司「お〜、ほんとにあんこがすっきりしてるね。これは男性や甘いものをあまり食べない人にもうれしいね。」
筆者「あんこのべたっとした甘さが苦手な人もいますもんね。もち米が柔らかめなのもあって食べやすいです。」
毎日その日に使う分を4時間かけて仕込んでいるあんこには、素材の風味を大切にするあづ木さんのこだわりが詰まっています。
素朴な美味しさの秘訣は、火加減や水の量の細かな調整、そして上白糖ではなく氷砂糖を使用すること。
これによって小豆の風味を最大限に引き出した優しい甘さに仕上がるのです。
このまま何個でも食べられそうなくらい、ほっとするような優しい味わいです。
続いて画像中央、八町もちやさんのおはぎ。
あんこ、きなこ、ごまの3種類の味がありますが、まずはあんこのおはぎから。

(3個入り・390円)
見た目はオーソドックスな俵型であんこの粒感は少な目で存外つるんとした見た目。
一方、もち米の粒感は比較的強く残っています。
食べ応えあるもち米をかみしめるたびに、くちどけの良いあんこの甘さがいっぱいに広がります!
上司「懐かしい味だ、The・おはぎって感じ。甘さは強いんだけれどどこか塩味も感じるかな。」
筆者「これぞ定番って感じですよね!もち米がしっかりしているからこそ、あんこの柔らかさが引き立ちますね。」
甘味と塩味の絶妙なバランスが引き立つ、これぞ正統派!という王道のおいしさです。
せっかくなので、ごまときなこのおはぎもいただきます。
まずは黒のすりごまが贅沢に使われているごまのおはぎ。
口の中に一気に広がる黒ごまの豊かな風味が、あんこの甘さとほど良くマッチ!
筆者「わ!ごまの風味がすごくいいですね。鼻に突き抜けてくる……」
上司「初めて食べたけど、中華のごま団子とはまた違う感じなんだね。ごまの香りが強いからあんこ感はかなり和らぐかな。」
黒ごまの香ばしさに、ついもう一個と手が伸びてしまいそうな魔力を感じます。
最後はきなこのおはぎ。粉が飛び散らないように注意しながら口に運びます。
筆者「あれ、なんか甘く……ない?」
口の中に一気に広がる大豆本来の風味。後から追いかけてくるあんこが甘いからこそ、きなこそのもののほんのりとした甘みが感じられます。
上司「多分、きな粉に砂糖を使ってないのかな。3つの中だと一番控えめな感じだ。」
予想に反して甘さが控えめなきなこのおはぎ。「普通のおはぎは甘すぎる」という方にぜひ食べてみていただきたいですね。
あんこ、きなこ、ごまの三者三様の味わいを楽しんだところで、三つ目の和菓子の登場。
画像の一番左、餅昌さんの商品をご覧ください。

(一個・170円)
あれ?なんかおはぎっぽくなくない?
画面の向こうで首を傾げているあなた、大正解です。
大粒の豆が周りを覆っているこのお菓子……実はおはぎではありません。
こちらは「かのこ」という、餅を包んだあん玉の外側に蜜漬けした豆を隙間なく並べた和菓子。
冬の寒い時期におはぎを食べる時、あんこが唇に触れて冷たさを感じることがあります。
そのせいか暖かい時期と比べるとおはぎの売り上げが落ち込んでしまう。
そんな理由から、餅昌さんでは代わりにかのこを販売しています。
「おはぎは今置いていないんです。」とお聞きした際には驚きましたが、こんな興味深い理由があったのです。
一体おはぎとかのこにはどんな違いがあるのか?いざ実食。
筆者「ほんとだ、冷たくない。」
唇に触れた豆からは冷たさを全く感じません。
表面にある大粒の豆の存在感とは対照的な口溶けの良いこし餡。
そして最奥に包まれたお餅は、まるでとろけるような柔らかさ。あっという間に口の中で消えてしまいました。
上司「豆!って感触がすごいね。優しいけどしっかり甘さは感じるね。」
筆者「中のお餅がすごくとろっとしてて……するっと食べちゃいました。」
見た目は一見おはぎと似ていますが、異素材のマリアージュが新感覚で楽しい和菓子。
かのこの発祥は江戸時代とのことですが、こんな面白い和菓子が300年以上前にも存在していたのか……。
これまでかのこを知らなかったという人にも、ぜひ一度味わっていただきたいですね。
それぞれのおはぎが持つ特徴についてまとめてみたので、ぜひ比べてみてください!

【File2:いちご大福】そのいちご、主役かエースかラスボスか
続いては、冬から春にかけて売り出されるあの愛され和菓子・いちご大福をご紹介。

(左から餅昌さん、八町もちやさん、あづ木さん)
今度は正真正銘、全ていちご大福です。
しかし見てわかる通り、それぞれ見た目が全然違うんです!
艶やかないちごの赤色にすっかり目を奪われてしまった筆者は、八町もちやさんのいちご大福をトップバッターに抜擢。

(3個入り・660円)
大福の切れ目から真っ赤で大きないちごがのぞく、魅惑的なビジュアル。
食欲を掻き立てるずるい見た目に我慢の限界、いちごの先端から一思いにかぶりつきます!
その瞬間。
口の中に広がる、じゅわっ、という音が聞こえてきそうな果汁感。
いちごの酸味と相反する甘いあんこ、それらすべてを包み込む純白の餅生地。
お餅はまるで赤ちゃんのほっぺのようにもちもち。至福、という言葉はこの瞬間のためにあるのだと思います。
上司「果汁が……すごい!下の大福が果汁を受け止めるために存在してる感じ。」
筆者「いちごに程よく酸味があるからこそ、おはぎのあんこの甘さが引き立っていますよね。」
やや甘めのあんこは大粒いちごのインパクトに負けない存在感を放っています。
甘さがなくいちごとあんこの個性をより引き出しているお餅は、一方で自分自身ももちもちな触感を武器に唯一無二の魅力を放つ……まさしく全員が主役なんです。
いちごと小豆、もち米が一体となって織りなす、幸せなハーモニー。是非味わっていただきたいです。
続いてあづ木さんのいちご大福をいただきます。
豊橋市の地元農家「まるきんファーム」で生産されたいちごを、お餅とあんこですっぽり閉じ込めていて非常にボリューミー。

(1個・340円)
半分に割ると、中に隠れたいちごがちらり。

真っ白な大福を割り開いて初めて現れるいちごの断面に、なぜ人はこんなにも心惹かれるのでしょう。
いちご大福をはじめとしたフルーツ大福は、断面の美しさを楽しむことも一興ですよね。
断面の美しさは100点満点ですが果たしてお味の方は……?
上司「求肥はほど良い厚さでしっかりしてるね。手で持った感触が違う。」
筆者「いちごそのものが甘くて美味しいですね……!単体で食べちゃいたいくらい。」
このあづ木さんのいちご大福、いちごがとにかく甘くて美味しいんです。
八町もちやさんのいちご大福が3人チームによる冒険活劇ならば、あづ木さんのいちご大福は1人の主人公の軌跡を追うヒューマンドラマとでもいうべきでしょうか。
主人公はあくまでいちごであり、お餅やあんこは良き親友やライバルのように寄り添っている、そんな印象を受けました。
素材であるいちごのおいしさを楽しむことができる、あづ木さんだからこその一品。
まるきんファームさんのいちごも食べてみたくなってしまいます。
いちご大福もついに残り一つに。

(1個・250円)
餅昌さんのいちご大福は小ぶりな見た目。
すっぽりといちごが包まれているにもかかわらず、赤いいちごの色が透けて見えるのは白あんを使っているから。

使われているいちごの品種は日替わりの様子。みくのかという品種は初めて聞きました。
一体こちらはどんないちごなのか。断面チェックと行きましょう。

しかしここでかなり苦戦。求肥が柔らかすぎて半分に切るのも一苦労です。
八町もちやさんのもちもちとした柔らかさとはまた別種の……ふわとろとでも形容すべきでしょうか。手で持つだけでもそんな柔らかさを感じます。
口にいれたら一体どうなってしまうのか……いざ、いただきます。
餅が……溶け、た……!?
筆者「なんかもはやお餅の美味しさを楽しむものな気がします、そのくらいお餅が天才。」
上司「これまでのいちご大福とはいちごの立たせ方が違うね。あんこは本当にいちごを支えるためだけにある感じ。」
あんこがいちごを引き立てている、という点ではあづ木さんのいちご大福とも共通していますが、餅の役割がまるで違うのです。
そのくらい筆者にとって、この柔らかさは衝撃でした。
もはや、メインであるはずのいちごが喰われてしまっていやしないか、と。
いちごがボスだと思っていたら本当のラスボスはお餅だった……そんな印象です。
いちご大福のスタンダードからは外れているものの、紛うことない名品と言えるでしょう。
みなさんはどのいちご大福が気になりましたか?もう一度特徴を振り返ってみてください。

【番外編】舌がびりびりするのも「味」だよねッ!
餅昌さんでこんなお話を伺いました。
「うちの商品は保存料などを添加していないから、羊羹のように砂糖をたくさん使っているようなお菓子以外は基本的に賞味期限が当日中です。
中でもいちご大福はもう別物になってしまうんですよ。」
「やっぱりいちごは生ものだからですか?」
うなずく餅昌さんのおかみさん。
「時間が経つにつれていちごの酵母とあんこの糖分が反応して、炭酸ガスができるんです。
それが大福の中にたまってしまうので、食べたときにシュワシュワした感じがしたり、こんな風に見た目に現れたりするんです。
時間がたつとお餅も多少硬くなってしまいますし。」
思えば筆者も、昔いちご大福を食べたら舌がビリっとしびれたことがありました。
てっきり酸っぱいいちごを使っているからだと考えていましたが、まさかそんな化学反応が起きていたとは。

(取材日前日に作られたいちご大福。右側のいちご大福は左下部分に炭酸ガスが溜まってしまっています。)
今回特別に、お店に並ぶことのない2日目のいちご大福を食べさせていただきました。
上司「ほんとだ!いちごがしゅわしゅわするってこういう感じか……。」
筆者「酸っぱいというより、舌に刺激がきますよね。お餅はあのとろとろ感はないけど、それでも十分柔らかいですね。」
持った時にお餅が指に引っ付いてしまいそうな柔らかさに比べると、確かに硬い。
しかしそれでも他の二店舗よりもややお餅が柔らかいような気がします。
人によってはこちらの方が好みかも……?なんて思いながら完食。
(※賞味期限の切れた商品を食べることを推奨する意図はございません。)
摩訶不思議な和菓子の世界、また一つ新たな扉を開いた気がします。
【File3:おすすめの一品】No.1なんて決められない!各店が誇るオンリーワンの魅力とは

(左から、餅昌さん、八町もちやさん、あづ木さん)
餅昌さんの「ういろう(黒)」
冒頭でも触れましたが、餅昌さんのういろうは戦前から同じ製法で作られており、まさにお店の歴史を象徴する一品。
商品は黒と白の二種類ありますが、今回は創業当初から作られている黒糖風味のういろう
をいただきます。

(一本・200円)
一本がかなり大きいので、1/4ほどの大きさに切っていただきます。
ほのかな甘みと黒糖の風味が、あんこの甘さが残る口内にすっと溶け込みます。
甘みはきちんと感じるものの、まったく飽きが来ない優しいお味。
筆者「これならいくらでも食べられる……もちもちでしあわせ……」
上司「ずっとまんじゅうを食べてたからね、黒糖のうまみはあんこのおいしさとはまた異色だよね。」
実は当日の朝一番には、こちらのういろうを10本一気に買っていかれたお客さんがいたのだとか。それだけ愛されているのも納得の美味しさです。
・八町もちやさんの「いがまんじゅう」
続いては八町もちやさんから、いがまんじゅうをいただきます。
「そもそもいがまんじゅうって何ぞや?」と思った方もいるでしょう。
筆者と上司は尾張地方の出身のため、実は今回初めていがまんじゅうを知りました。
それもそのはず、いがまんじゅうは愛知県の中でも西三河地域独自の風習として食される雛祭りの行事食なのだそう。
他にも愛知県には「おこしもん」という雛祭りの行事食もあります。
尾張と三河の食文化の違いがこんなところにも現れているのですね。

(3個入り・420円)
「当店では季節のものや四季折々の素材を利用したお菓子を先取りしてお出ししています。
季節の到来を感じて楽しんでいただきたいので、本日はいがまんじゅうをご用意しました。」
粒あんまたはこし餡を米粉で包んだオーソドックスなお餅。
その表面を彩るピンク色の粒々は着色されたもち米。色合いから春を感じられますね。
西三河の伝統の味をいざ、いただきます。
筆者「このピンクの粒って固くないんだ!もっとカリカリなのかと思った……」
上司「固めのもち米だったね。お餅そのものは柏餅とかのあの感じだ。」
しっかりと噛み応えがあるお餅としっとり重厚感のあるこしあんに、子ども時代にタイムスリップしたような懐かしさを感じました。
堅実で王道の餅菓子という印象です。
・あづ木さんの「豆大福」
大トリを飾るのは、あづ木さんの豆大福。
真っ白で大きな大福にうっすらと透ける豆の色。
かの雪の妖精、シマエナガを思い出すのは私だけでしょうか。

(1個・240円)
看板商品であるこの豆大福ですが、実は一つ他の店とは異なる点があるんです!
それは、北海道産の黒豆を使用していること。
一般的な豆大福に使われているのは赤いんげん豆という種類。
しかし豆大福の開発にあたって店主さんが試行錯誤した結果、「一番美味しかったから」という理由で黒豆を採用したのです。

このように大粒の黒豆がごろごろ。あんこも粒感たっぷり。
むっちり肉厚できめ細かい大福とのコントラストがなんとも美しい……。
ああ、今すぐかぶりつきたい……!
筆者「甘みと塩気が絶妙すぎます。ずっと言ってるけどこれはほんとに何個でも食べれる。」
上司「塩味がめっちゃいいよね。お餅や豆の歯ごたえがあるから食べた感がある。」
大きな福、という名を体現する、圧倒的幸福感。
こだわりのあんこは甘すぎず、飽きずに食べられるからこそ、最後まで美味しく食べられます。
お腹を空かせて学校から帰ってきたお子さんのおやつに、働く人々が仕事終わりまでのあと数時間を頑張るためのエネルギー補給に。
あらゆるおやつシーンに優しく寄り添ってくれる、あづ木さんの豆大福はそんな存在であると感じました。
それぞれお店の特色が表れているおすすめの一品。ぜひそれぞれの特徴を比べてみてください!

我々の和菓子探求はこれからだ!
9種類のお菓子をいただきましたが、皆さんはどの商品が気になりましたか?
一言に和菓子といっても、それぞれのお店が築いてきた味があることがお判りいただけたと思います。
しかし、どんなお店にも共通する想いがあります。
それは、「地域の人々に長く愛されるお店でありたい。」ということ。
「うちの商品を懐かしがって買い求めてくださるお客様が多くいらっしゃるので、できるだけ長く続けていきたい。」
そう語る餅昌さん。

(戦前から続く「餅昌」の味を守っていく大黒柱。)
「これからも今まで通り地域の方に愛してもらえるお店にしていきたいですね。」
強い決意をにじませる八町もちやさん。

(もうすぐ100年の歴史を迎える「八町もちや」を切り盛りする4代目当主。)
「地元の方に喜んでもらえるお店にしたいです。子どもがお小遣いをもって買いに来てくれるような、そんなお店に。」
そう言って笑みを浮かべるあづ木さん。

(一人で和菓子を作られている店主を支えるご夫人。)
その土地に暮らす人々の生活に寄り添い、愛おしい過去の記憶の一部に刻み込まれる。
そんな味を届けるために、今日も和菓子を作り続ける匠の姿がありました。
毎日のおやつタイムを共に過ごしたい。
将来、子どもや孫と一緒に「おいしいね。」と笑い合いながら時間を分かち合いたい。
そんな風に思えるあなただけの特別な味を探しに、和菓子の世界へ足を踏み入れてみませんか?
素敵な店主さんたちが、あんこのようにあなたを優しく包み込んでくれることでしょう。
Shop Info
「ういろう 餅昌」
| 住所 | 〒440-0085 愛知県豊橋市下地町2丁目60 |
| 電話番号 | 0532-52-6538 |
| HP | https://sites.google.com/view/motimasa |
| SNS(Instagram) | @uiroumochimasa |
| 営業時間 | 10:00〜18:00(売り切れ次第終了) |
| 定休日 | 水曜日(不定期に火・水連休あり) |
| 駐車場 | 2台(店舗向かって左方向20m先) |

このような看板が立っており、手前側の1・2番が餅昌さんの駐車場となっています。
「八町 もちや」
| 住所 | 〒440-0806 愛知県豊橋市八町通5丁目73 |
| 電話番号 | 0120-051-281 |
| SNS(Instagram) | @hatcho_mochiya |
| SNS(X) | @8mochiya |
| 営業時間 | 8:00〜 売り切れ次第終了 |
| 定休日 | 不定休(SNSをご確認ください) |
| 駐車場 | 3台(店舗裏手側) |

お店の入り口に面している表通りから一本奥に入ると、こちらの看板が立っています。
周囲は一本通行の道路が多いため、道路標識に従ってご通行ください。
「和菓子 あづ木」
| 住所 | 〒441-8082 愛知県豊橋市往完町郷社東9-3 |
| 電話番号 | 0532-31-3150 |
| HP | https://wagashi-azuki.com/ |
| SNS(Instagram) | @azuki2021616 |
| 営業時間 | 9:00~18:00(売り切れ次第終了) |
| 定休日 | 日曜日・月曜日 |
| 駐車場 | 3台 (店舗前1台、 店舗を背に左斜め向かいに2台) |

店舗前にはこのように貼り紙があります。
はす向かい側にある駐車場は初めて来店される方には少しわかりにくいかも。
周辺の電柱には店舗への道順が書かれているので参考にしてください!